このブログでは、「人と動物が健康で幸せな社会をつくる」という夢のもと、飼い主さんとペットの暮らしに役立つ情報を発信しています。
もし記事が少しでも参考になったら、Xでシェアしたり、ブックマークしていただけると嬉しいです!
はじめに|「避難のとき、うちの子はどうすれば…?」
台風や大雨、地震などで避難が必要になったとき、「ペットをどうやって連れていけばいいの?」「何を用意しておくべき?」と不安を感じる飼い主さんも多いのではないでしょうか。
災害はいつ来るかわからないからこそ、普段からの備えが大切です。
今回は、飼い主さんとペットが安心して避難できるための準備や、避難時の注意点を解説します。
防災の第一歩!まずは何を準備するべき?
災害時、ペットの安全は飼い主さんの準備にかかっています。
しかし、実際には「何を用意すればいいのかわからない」という方も少なくありません。
2023年にアイペット損害保険が行った調査では、環境省のガイドラインで「同行避難が原則」とされていることを知っている人は**わずか23.5%**でした(調査結果はこちら)。
まだまだ避難のための情報が行き届いていないのが現状です。
ここですぐに実行できる準備について確認してできる所から準備をすすめていきましょ
事前に用意すべき防災用品
犬猫共通の必需品
- 療法食や普段食べているフード(5日分以上)
- 水(1日あたり体重1kgにつき50〜60mlを目安に)
- 普段飲んでいるサプリメントや常備薬
※心臓病や腎臓病など長期投薬が必要な場合、切らさないようかかりつけ医に相談しましょう! - 食器や紙皿
普段のペット用品
- ペットシーツ
- ケージやキャリーケース(避難所では必須の場合が多いです)
- タオルやブラシ
- 遊び慣れたおもちゃ
- ブランケット
犬向けに追加で必要なもの
- 予備の首輪や伸びないタイプのリード
- 狂犬病予防接種証明書
- 鑑札(首輪に常時装着が義務になっています)
猫向けに追加で必要なもの
- 目隠し用のタオル
- 洗濯ネット(目の細かいもの)
→ 暴れてしまっても入れておけば自分や周りの人、ネコちゃんをケガさせることがなく安心です。脱走防止にもなり移動もしやすくなります!
もしもの時のために、しつけや健康管理を
避難所では、動物が苦手な人やアレルギーがある人、興味を持って近づく子どもなど、普段と異なる人間関係の中で暮らすことになります。
そのため、次の準備を日頃から行っておきましょう。
- クレートトレーニング:キャリーやケージで静かに過ごせる練習
- 吠え癖や噛み癖の改善:必要に応じてドッグトレーナーに相談しましょう
- 予防接種・寄生虫予防:狂犬病、混合ワクチン、ノミ・マダニ予防は必須です
[予防接種やノミダニの予防についてはこちらの記事をご覧ください→内部リンク]
マイクロチップは大切な身元証明
装着義務があるマイクロチップは、万が一逃げ出してしまった場合の身元証明に有効です。
登録情報が最新になっているかも定期的に確認しましょう。
ペットと安全に避難するためには?
まずは飼い主さん自身の安全が第一です。
飼い主が無事に避難できなければ、ペットも避難できません。
同行避難と同伴避難の違い
- 同行避難:ペットと一緒に避難行動をとること(避難所以外の安全な場所も含む)
- 同伴避難:避難所でペットと同じ空間で生活すること
環境省は「同行避難」を原則としていますが、必ずしも同伴避難ができるわけではありません。
そのため、ペットと一緒に滞在できる避難所や施設を事前に確認しておくか、避難所以外で避難生活をする方法を考えておきましょう!
避難所の場所はどこ?動物避難所マップを活用
市区町村の防災ページや「動物避難所マップ」で、近隣の受け入れ可能な避難所を確認できます、、
できれば2〜3か所候補を見つけておくと安心です。
避難所での生活で注意すべきこと
避難所には、動物が苦手な人・アレルギーのある人・犬猫に慣れていない人もいます。
また、ペット自身も慣れない環境でストレスを感じやすくなります。
- 他の人やペットとの距離を保つ
- 排泄後は必ず清掃・消臭
- 無駄吠え防止のため、十分な休息と安心できる環境を用意
- 食器やトイレは清潔に保つ
まとめ|人もペットも安全に避難するために
災害は突然やってきます。
だからこそ、「物の準備」「しつけ・健康管理」「避難先の確認」の3つを日頃から整えておくことが大切です。
ペットは自分で安全を確保できません。
飼い主さんの準備と判断が、命を守ります。
今日から少しずつ、できることから始めていきましょう。
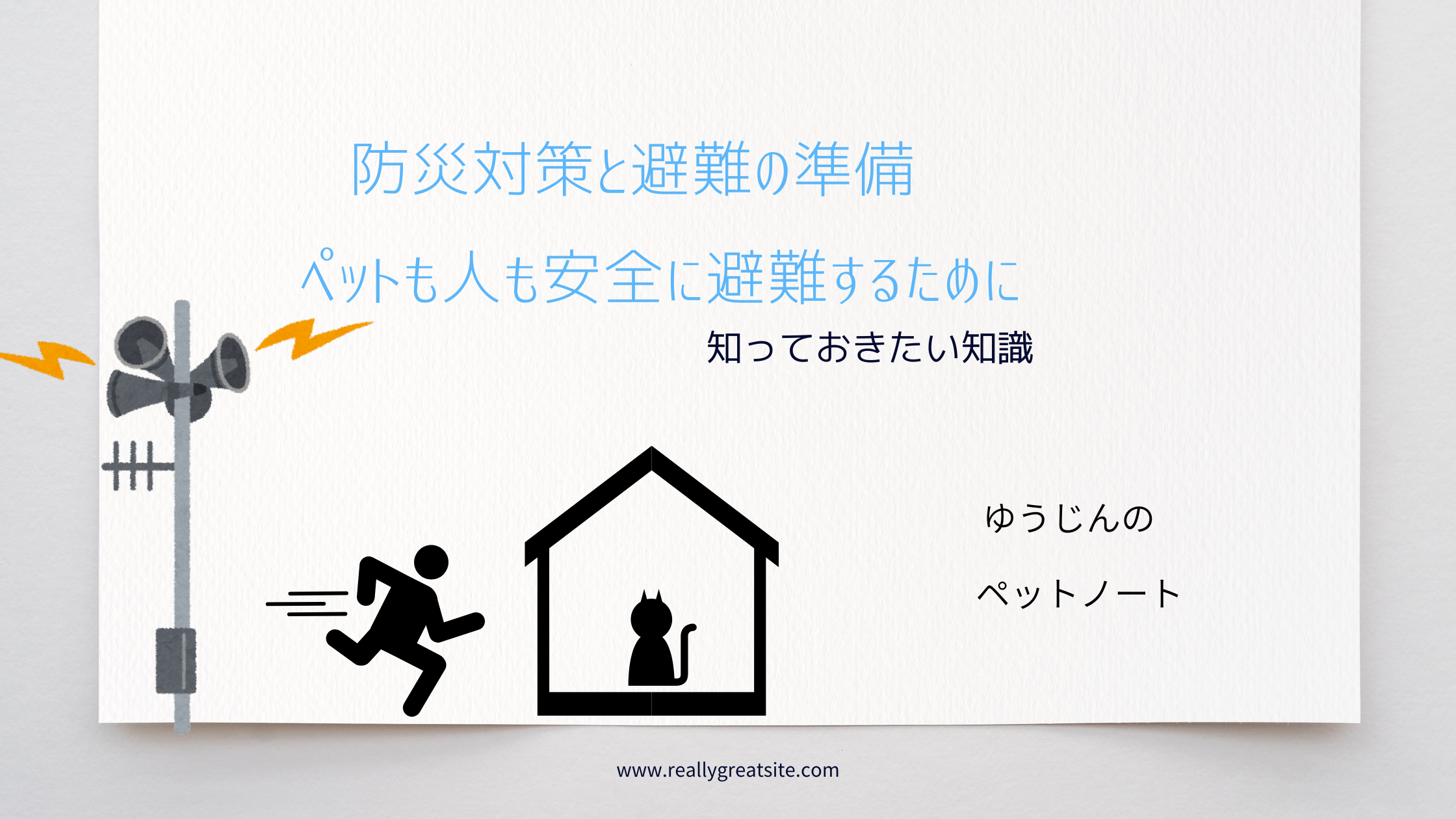
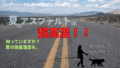
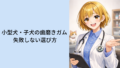
コメント