このブログでは、「人と動物が健康で幸せな社会をつくる」という夢のもと、飼い主さんとペットの暮らしに役立つ情報を発信しています。
もし記事が少しでも参考になったら、Xでシェアしたり、ブックマークしていただけると嬉しいです!
はじめに|耳そうじ、実は「やりすぎ注意」って知ってましたか?
梅雨時や夏は、湿気や気温の上昇で「外耳炎」が増える季節。
動物病院でも「耳を気にしている」「耳が赤い、臭う」といった相談が多くなります。
でも、「毎日耳そうじしてます!」という方ほど、実は耳のトラブルを起こしやすいことも。
耳そうじは、正しい頻度とやり方を知ってこそ、健康管理としての効果を発揮します。
犬猫の耳そうじは必要?|「必要だけど、やりすぎはNG」
犬猫の外耳道(耳の穴の構造)はL字型に曲がっていて、汚れや湿気がたまりやすい構造になっています。
とくに以下のような子は、定期的な耳のケアが推奨されます。
- 垂れ耳の犬種(例:ダックス、コッカー、ビーグルなど)
- アレルギーや皮膚トラブルが出やすい子
- 耳が蒸れやすい環境(夏場、シャンプー後など)
ただし、健康な耳に毎日の耳そうじは不要です。
やりすぎると、皮膚を傷つけたり、逆に炎症を起こしてしまう原因になることもあります。
耳そうじの頻度とチェックのポイント
■ 理想の頻度は?
- 健康な耳:月1〜2回程度のチェックと軽いケアでOK
- 耳垢が多い/汚れやすい:週1回を目安に、獣医師と相談して頻度調整を
■ 耳の状態チェックのポイント
- 耳の中が赤くないか?
- 匂いが強くないか?
- 耳垢が黄色〜茶色で、量が多くないか?
これらが気になるときは、耳そうじの前に病院での診察をおすすめします。
正しい耳そうじのやり方
STEP1|準備するもの
- 犬猫用のイヤークリーナー(市販品または動物病院で処方されたもの)
- コットンまたはガーゼ
- おやつ(ご褒美用)
STEP2|やり方の流れ
- イヤークリーナーを耳の穴に直接数滴垂らす
- 耳の付け根を軽くもみもみとマッサージ(「くちゅくちゅ」と音がするくらい)
- ペットがブルブルと頭を振るので、出てきた汚れをコットンで拭き取る
💡注意:綿棒はNG!
耳の奥を傷つけたり、汚れを押し込んでしまう可能性があります。
こんなときは要注意|耳そうじでは改善しないサイン
- 耳から黄色や黒い分泌物が多量に出る
- 強いにおいがある
- 頻繁に頭を振ったり、耳をかゆがる
- 耳が赤く腫れている、熱を持っている
これらは外耳炎や耳ダニ、真菌感染の可能性もあります。
耳そうじでの対処はやめて、早めに動物病院で診察を受けましょう。
まとめ|「やらないと不安」より、「正しくやる」が大切
犬猫の耳そうじは、体調管理のひとつ。
でも、「きれいにしなきゃ」と毎日ゴシゴシするのは逆効果になることもあります。
- 月1〜2回のチェックと、必要なときのケア
- 専用のクリーナーを使って、やさしく拭き取るだけ
- 異常があれば、無理せず獣医師へ相談!
正しいケアで、快適で健康な毎日を一緒に守っていきましょう。
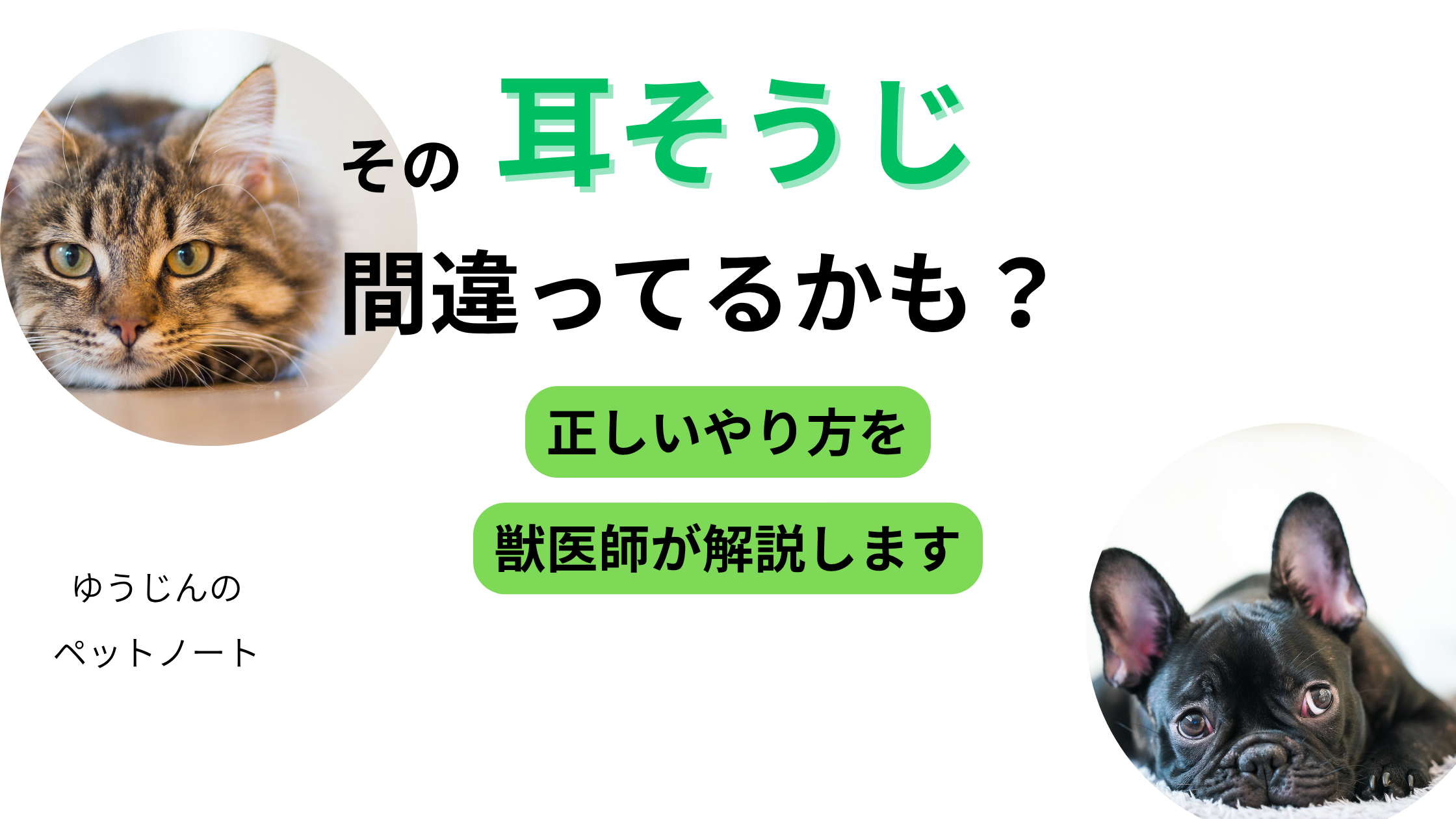
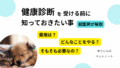

コメント